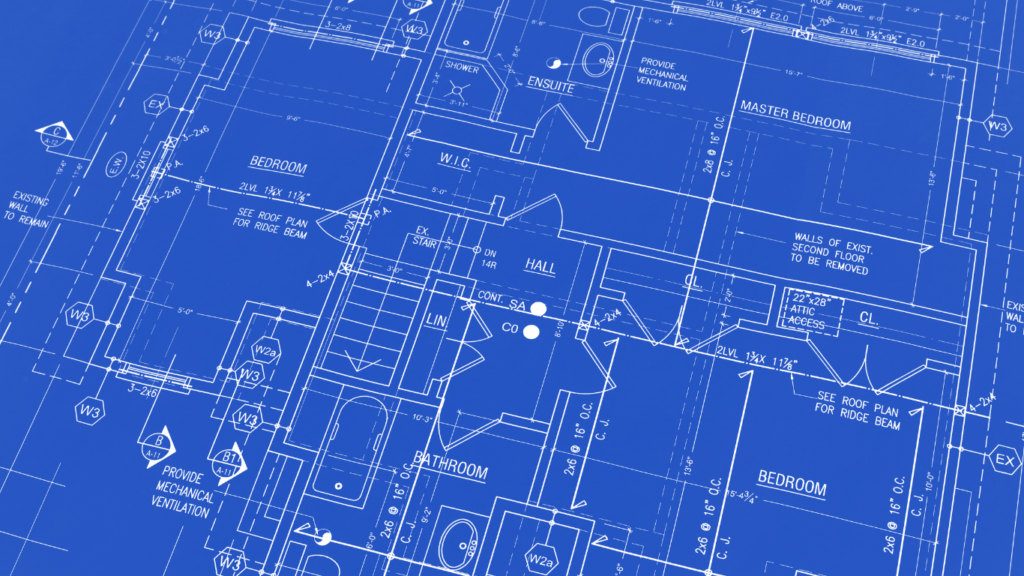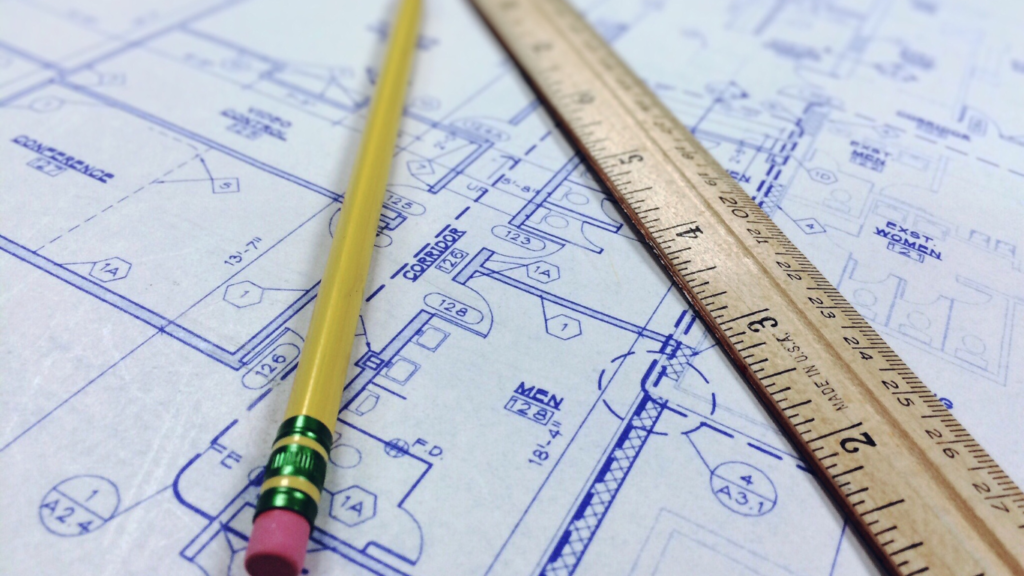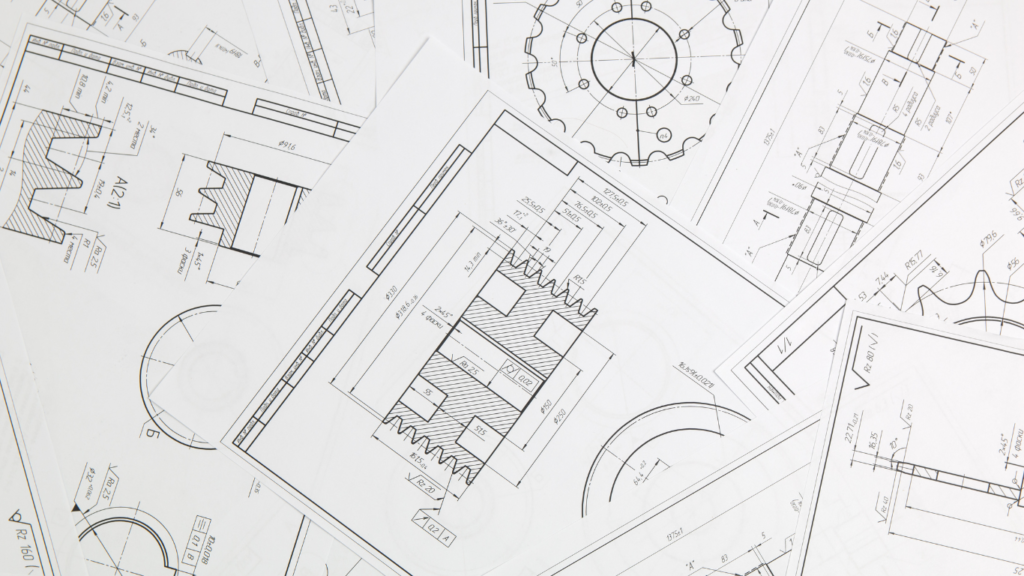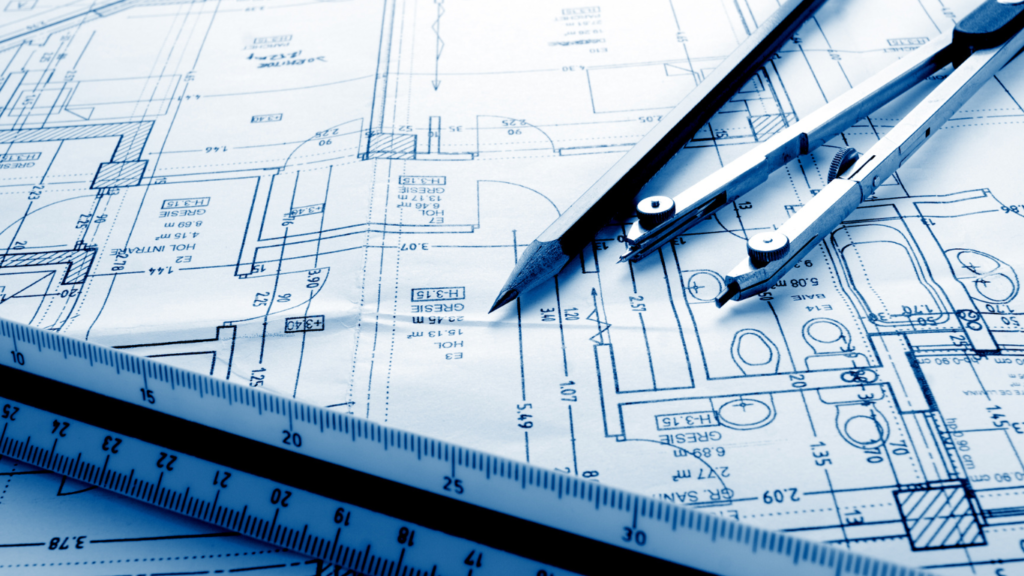
当サイトで、「マイクロ法人」というキーワードが時々出てきます。マイクロ法人を活用すれば、たしかに社会保険料を節約したり、法人を利用することで、各種の節税対策を行うことができます。しかし医師がマイクロ法人を使うというケースを考えると、私個人としては、コストパフォーマンスが悪く、少なくとも多くの先生向けではないと考えています。マイクロ法人そのものに各種維持費用がかかりますし、書類の届け出等の事務仕事が増えます。医師の時給を考えれば、こんな回りくどいことをするくらいなら、優良なスポットバイトをしたほうが効率が良いです。
今回は勤務医がマイクロ法人を使うというケースについて考えていこうと思います。
マイクロ法人とは?
マイクロ法人そのものについては、リベ大等のYouTube、ブログでわかりやすく解説されているので、そちらを見ていただくのが一番早いです。(→参考記事)
簡単に言えば、先生が一人社長のプライベートカンパニーを作り、法人から先生に支払う給与を最小限にすることで、標準報酬月額を抑え、社会保険料を節約するという手法です。一度、標準報酬月額が固定されれば、他の非常勤でどんなに高給をもらおうと社会保険料は変わらないという、制度の抜け道をついた手法になります。
また執筆や講演など、診療以外の収入を法人の売上として、法人経費を上手に使用することで、節税を行えます。売上が多い場合は、借り上げ社宅の制度を使用し、先生個人の家賃も節約することが合法的に可能です。
注意が必要なのは、給与所得を法人に振り込ませることは出来ないという点です。医師の場合は、診療に関わること、産業医業務などは給与所得とみなされ、これらの所得を法人に振り込ませて事業所得にして節税するのは不可能になります。給与所得を法人の事業所得に振り返ることができない点は、マイクロ法人の落とし穴の一つです。
マイクロ法人は非常勤の先生が考慮する手法
医師がマイクロ法人を使うケースは、基本的には非常勤で勤務されている先生です。非常勤を掛け持っている先生は、社会保険としては、国民健康保険+国民年金に加入することになります。非常勤をいくつかけもっている場合、国民健康保険は上限マックスになる可能性が高く、所得控除は使えるものの、かなりの負担になります。
このようなケースでマイクロ法人を使った戦略を行うと、社会保険料が
国民健康保険 + 国民年金 → 健康保険 + 厚生年金
に振り替えることが可能であり、同時に非常勤の高給と切り離して考えることができるため、結果として社会保険料を節約することができます。
常勤で勤務されている先生は、常勤先の病院で社会保険に加入しているので、マイクロ法人を作っても社会保険料を節約することは出来ません。むしろマイクロ法人から給与を出すと、社会保険料の計算が複雑になり手に負えないことになるため、おすすめできません。マイクロ法人は常勤の所属先がある先生にはメリットが乏しい手法です。
マイクロ法人のメリット・デメリット
マイクロについては、色々な考え方がありますが、医師の立場からメリット・デメリットを考えて見ようと思います。
マイクロ法人のメリット
社会保険料の削減
マイクロ法人を行う場合、まず挙げられるメリットとしては、社会保険料の削減です。社会保険料は、マイクロ法人から先生に支払う給与に連動します。正確には標準報酬月額に連動するので、給与を社会保険料が払えるギリギリに設定することで、節約することが可能です。
非常勤の先生が一般的に加入する社会保険は、国民健康保険+国民年金ですが、国民年金のほうが一定であるものの、国民健康保険は収入に連動します。先生の給与では上限マックスになり、居住地域にもよりますが、介護分を含めると年間100万円を超える負担額になります。これはかなり重い税金です。これを削減できることはたしかに大きなメリットです。
またマイクロ法人による社会保険料の節約は、扶養家族がいる場合さらに加速します。配偶者を第3号被保険者にすることで、扶養扱いにすると、国民年金も含めて支払いが免除されます。配偶者の所得が一定以下の場合は大きなメリットになります。またお子さんがいる場合も、健康保険の場合は、扶養家族とできるので、保険料も据え置きです。
高額療養費の上限が低い
これは隠れたメリットですが、高額療養費についても先生の非常勤を含めた所得に連動するのではなく、標準報酬月額に連動します。そのためマイクロ法人の場合、「区分エ」に該当するため、万が一先生が入院、手術を受けて医療費がたとえ何百万円かかっても、月の医療費の上限は、なんと6万円以下で済みます。しかもこれは扶養家族にも適用されます。簡易的な医療保険の代わりになるので、これがあれば民間の医療保険はほぼ不要だと思います。これは何故かマイクロ法人の情報を扱うサイトでもあまり触れられませんが、結構なメリットであると考えます。
法人経費による節税
法人に売上があれば、法人の経費を、業務に関わる範囲であれば使用することが出来ます。税引前のお金を使って、経費を計上することで、結果的に節税になります。マイクロ法人では先生がひとり社長ですから、経費の使い方に文句を言う人はいません。先生が法人業務に関わると判断し、会社に必要と判断すれば、経費として使用できます。
代表的なもので言えば、書籍やパソコンなどのIT機器でしょうか。もちろん全く法人の方に関係無いものは経費にできませんが、実務上はあいまいなケースもあります。たとえば医療系のブログを法人の業務として行っている場合、その資料として医学書を買うことは普通ですし、そのブログを執筆するパソコンを購入することもできます。また通信環境も法人経費で用意することが可能です。
しかし経費については、前述のようにひとり社長であるが故に、ブレーキがかからない危険性があります。たとえば医療系のブログにピアノによる音楽療法記事を一つ書いたからといって、グランドピアノを購入しても経費としては認められないと思います。この場合は、せいぜい音楽療法の書籍が資料として認められるのが限界でしょう。いくら業務に関わると言っても、さすがに社会的な常識と照らし合わせる必要があります。
出張に経費が使える
また法人の経費で出張することが、もちろん可能です。出張については、出張の規定をあらかじめ定めておくことで、先生個人に資産を無税で移せる有利な制度があります。出張については、実際、本当に行っていれば取材や資料収集などの目的で認められるケースが多いようです。もちろん出張に行ったフリをして、経費を計上する「カラ出張」は嘘になるので、絶対にNGです。外出が好きな先生は、出張しつつ気分転換にもなり、なおかつ法人の経費で行けるので、結構いいかもしれません。
個人の家賃を法人に払ってもらう
これは非常に強力なものの、完全に合法な制度です。先生が住む賃貸住宅を「借り上げ社宅」として法人に借りてもらい、先生がそこに一定の負担をして住むことができる手法です。この制度を使うと、法人に家賃を8割方負担してもらい、先生個人は、残りの2割ほどを負担すれば良いことになります。法人の経費を使用して、個人の居住先を確保することができるので、非常に強力です。法人の経費も消費しつつ、先生の個人資産からの持ち出しも抑えることが可能です。
これは一定以上成功している人たちには有名な手法のようで、少なくないお金持ちが用いている手法です。お金持ちは、様々な節税手法が使えるので、さらに手元に残るお金が増えて、ますますお金持ちになるということでしょうか。資本主義のいびつな側面が垣間見える気がします。
資産運用での節税
株や投資信託での資産運用では、個人の場合、税金はおよそ20%です。しかし法人に個人資産を移して運用すると、経費が使えるので、上手に法人を経営すれば、結果的に節税が可能になります。上記のような家賃を負担してもらう手法や、個人でもほしい物で法人業務に関わるものであれば、法人に経費として計上してもらう方法が可能です。
個人の資産形成にある程度目処がついている先生は、余剰分を法人に移すことで上手に節税することが可能になります。
マイクロ法人のデメリット
上記のようにマイクロ法人にはメリットが多くあり、いいことずくめのように思えますが、実はデメリットも少なくありません。特に事務仕事が爆増するので、非常に面倒でつまらない仕事が増えることになります。以下でデメリットを見ていきます。
維持費用
マイクロ法人はたとえ赤字であっても税金が発生し、また会計ソフトなどの維持費用もかかります。しかも個人ではなく、法人扱いになると、いちいち費用が高額になります。マイクロ法人そのものにかかる費用が、少なくないということが大きなデメリットの一つです。
税金については、均等割として赤字でも年間75000円ほどかかることになります。また会計ソフトも年間 3-4万円、後述しますが、法人決算を自力で行う場合、「全力法人税」というソフトを使うケースでは、年間1-2万円かかります。特に何もしなくても、法人があるだけで、10万円以上の費用がかかり続けることになります。
また法人決算を税理士に依頼する場合は、さらに数十万円の費用がかかります。一般的に個人の確定申告は自力でもなんとかなりますが、法人の申告はかなり複雑です。自力で行うには、かなりの時間を投下する必要もあり、お金以外の手間や労力もかかることになります。
当然ですが、毎月のご自身への給与や、社会保険料の支払いも必要です。これらを総合すると、最低でも年間50万円弱の経費がかかります。社会保険料についてはマイクロ法人がなくても、他で負担するものなので、まだいいですが、冒頭の税金や会計ソフトの費用はマイクロ法人がなければ本来必要ない経費です。売上がない場合、個人資産から役員借入金として負担することになりますが、結構な負担になります。
医療以外の収入を確保しなければならない
マイクロ法人では、医師免許を使った診療以外の新たな仕事を確保しなければならず、これが多くの先生にとって高いハードルになります。元々執筆やブログで収益があるような先生は、それらを一度法人を通すようにすればいいので簡単ですが、一般的に勤務医が副業を持っているケースのほうが少ないです。新たにブログを始めたり、YouTubeを始めたり、コンサルタントの業務をしても、診療以外ならなんでもよいですが、収益化までに時間がかかるのが普通です。そもそも忙しい臨床を行いながら、副業で成果を出すのは、時間的な制約もあり、なかなか難しいというのが現実だと思います。
最初にも少し触れましたが、非常勤の給与を法人の売上として振り込んでもらうことは出来ません。給与所得と事業所得に振り替えることは禁止されているためです。厳密に言えば、診療の給与ではなく、たとえば病院のコンサルタントとしてアドバイスした場合や、職員の教育のために講演を行った料金を法人に振り込んでもらうのはOKですが、実際問題としてそんなことが可能な先生がどれだけいるでしょうか?また税務署の目も厳しくみられるので、誰がどう見ても普段の給与と明確に区別して、給与所得ではなく事業所得であると証明できる必要があります。本当は給与なのに、節税目的で一部を事業所得にしようとする人も中にはいるからです。
維持費用を賄うのだけでも大変
実務上は医師が片手間の副業で、法人を経営することは最小限の経費を払うだけでも大変であると思います。私も医師免許を使わずに収入を確保することが、いかに大変なことかを痛感しました。
個人資産が多くある先生は、一部を法人に移して資産運用すればいい
上記のようにマイクロ法人で収入を確保することは多くの臨床医にとってはハードルが高いものですが、個人資産が多い先生はこちらの問題はクリアできます。個人資産の一部を法人に移して、資産運用を行って得た収益を経費に充てればいいわけです。資産運用についても高配当ETF(VYM、 SCHD等)やそれに連動する投資信託を購入すれば、先生は何もせず放っておくだけで、年に4回分配金が振り込まれます。これで法人経費をまかなえばOKです。しかも資産運用の分配金は金融危機でも起こらない限り、ある程度は安定して振り込まれます。
しかしそもそも資産がある先生が、時間を使ってこんな回りくどいことをするメリットがあるのかという、別の問題が生じてきますが。。。
書類業務が面倒
マイクロ法人といえども立派な法人ですから、各種届出が必要になります。給与支払の報告、社会保険に関する手続き、そして最大の山場が法人税を含めた決算の業務です。これらの事務仕事にかなりの時間が取られます。しかも最初はわからないことだらけですから、負担も大きいです。
税理士に依頼するという手も現実的ではありますが、その場合、税理士費用がかかり、マイクロ法人経費のかなりの割合を占めることになります。決算だけ依頼する手もありますが、その場合でも少なくとも10万円以上はかかります。節税のためのマイクロ法人で、経費がかかると、結局手元に残るお金は大して変わらないということになりかねません。頭のリソースも取られます。先生のリソースは有料というか、高額です。マイクロ法人に先生が割く時間と、手元に残る節税の効果を計算した場合、先生の時給はいかがでしょうか?おそらくアルバイトの方がだいぶ高額なはずです。
私が冒頭でマイクロ法人を万人受けではないとしたのは、医師の場合は時給が高いため、マイクロ法人に関わる経費を差し引いて手元に残るお金のことを考えると、コストパフォーマンス的に割に合わない可能性が高いと考えるためです。
規制の可能性
いびつな制度の抜け道をついた手法であり、どこかの時点でメリットが封じられてしまう可能性もあります。特に社会保険料については懸念があります。今までも多くの法人を使った節税策があったようですが、そのたびに封じられてきました。今の時点ではなんとも言えない状況ですが、今後の動向には注意が必要です。
※例外的に、常勤の先生がマイクロ法人を使うケース
マイクロ法人の使用を考慮するケースは非常勤の先生と書きましたが、例外的に常勤の先生も使うケースも想定されます。それは社会保険料以外のメリットを享受したい先生です。かなりの資産があり、法人で資産運用を行って節税をしたい先生や、副業でかなりの収入がある先生が想定されます。また私は詳しくわかりませんが、不動産を持っている先生も使う余地があるようです。
まず常勤の先生の場合は、社会保険料は常勤で払ってもらっているので、こちらには触らないほうが無難です。法人から先生に払う給与を0円にすれば、マイクロ法人で社会保険に加入できないので、その点はクリアできます。社会保険料については常勤先にお任せしましょう。
資産運用や副業での収益を、上述の借り上げ社宅として経費にあてたり、出張の経費にしたり、個人でも手に入れたいもので法人に関係するものを経費で買うという使い方が想定されます。先生のプライベートカンパニーとして、好きなように使える法人をひとつ持っておくと、何かと便利なこともあります。
またお金があれば、面倒な事務仕事は外注してしまえばよいです。税金関係は税理士に依頼して、事務仕事も秘書代行サービスに依頼しても良いでしょう。ここまで来れば先生は面倒ごとからも開放され、メリットを多く享受できます。
結論は万人受けではない
マイクロ法人のメリット・デメリットについてご紹介してきましたが、結論としては、万人受けではないと私は思います。特に医師の場合は一般的な時給と考えると割に合わない可能性が高いです。
{(マイクロ法人での節税効果)ー(マイクロ法人にかかる費用)}/ (先生がマイクロ法人にかける時間)
が、アルバイトの給与を上回ることがあるでしょうか?きっと多くの先生にとっては、医師としての時給のほうが高いはずです。こんな回りくどいことをするくらいなら、スポットアルバイトを年に何回か行った方が、明らかにコストパフォーマンスが良く、労力も少ないです。
マイクロ法人が向く先生
話をまとめると、マイクロ法人が向く先生というのは、非常勤で医師の仕事をしており、なおかつ事務的な仕事を行うことに抵抗がない先生で、①すでに副業がある程度軌道に乗っていて定期収入が見込める先生、または、②かなりの個人資産を保有しており、法人で資産運用を行った方が税務上有利な先生、の2パターンとなると思います。
副業を持っている先生はいらっしゃいますが、それでも医師の中では少数派です。その中でも非常勤の医師というと、さらに限られると思われます。
またかなりの資産を持っている先生が、非常勤で勤務医を続けているのかも疑問です。、そのような先生が、未だに税務上何の対策も取っていないとも考えにくく、マイクロ法人よりもさらに有効なスキームを用いている可能性が高いでしょう。
しかし敢えて行うとわかるのでいいかも
ここまでご覧頂いて、多くの先生はマイクロ法人を作ろうとは思わないかもしれませんが、それでもやってみたいと思われる先生は、試しにやってみるのが良いと思います。理由としては、たとえマイクロ法人で上手く行かなかったとしても、嫌だと思えば辞めればいいだけだからです。マイクロ法人の設立や維持費用にはいくらかお金がかかりますが、失敗してもせいぜい数十万円の損失で済みます。株やFXのように、何百万円、何千万円も損失することはなく、一定の経験も得られると思えば悪くない投資です。数年運用してみて、やっぱり面倒だと思えば止めて、社会保険を切り替えればいいですし、社会保険の管理も面倒だと思えば、非常勤から常勤に移っても良いわけです。逆に法人を作ったことで、副業に熱意を持って取り組んで、思いも寄らない成果を挙げられるかもしれません。そうなればまた新たな世界が開けてきます。
電子書籍
本記事と同内容ですが、少し体裁を整えて電子書籍でも出版しました。kindle unlimited で無料で読めますので、併せてどうぞ。
『勤務医とマイクロ法人 : 医師転職を考え方4』