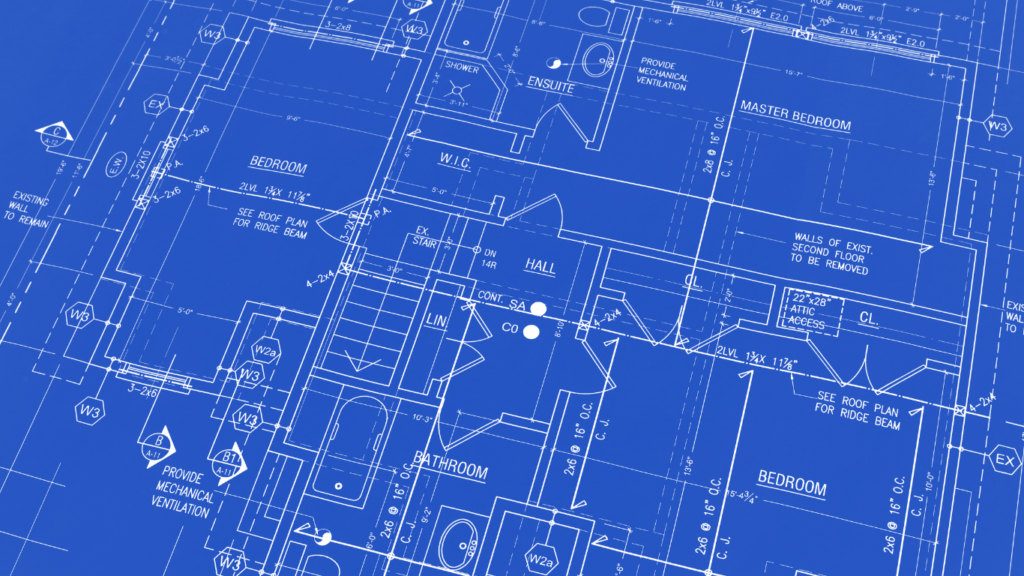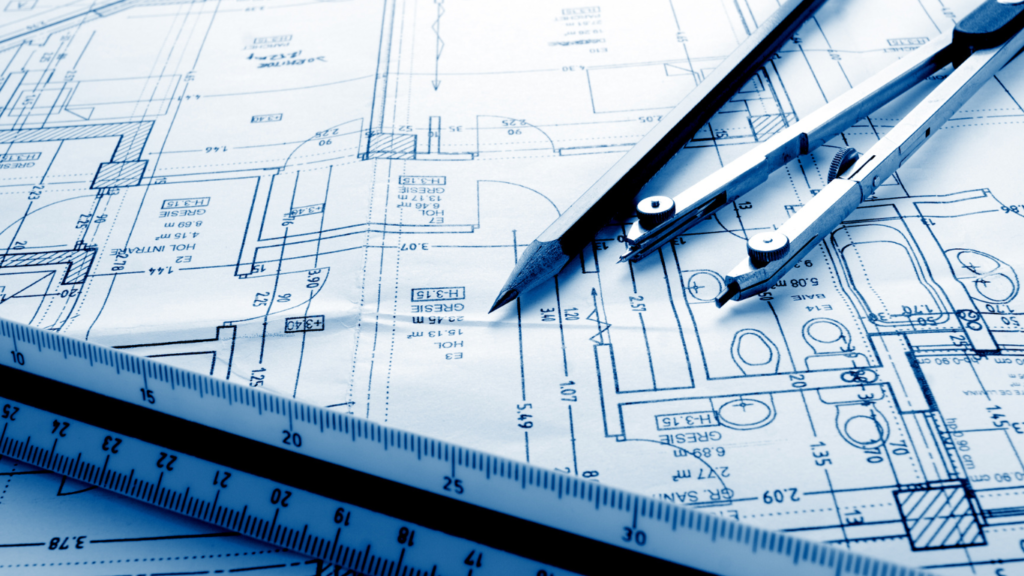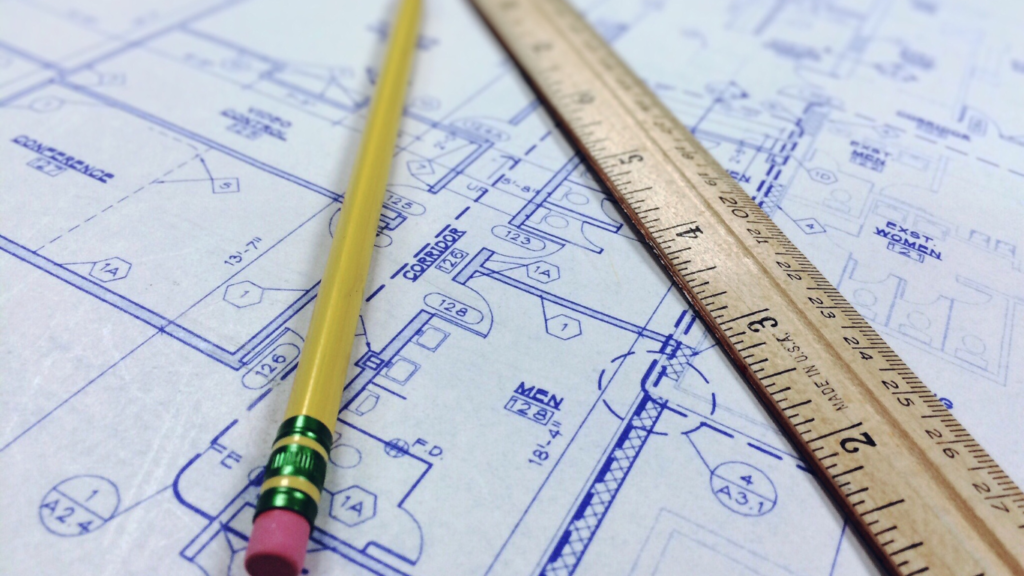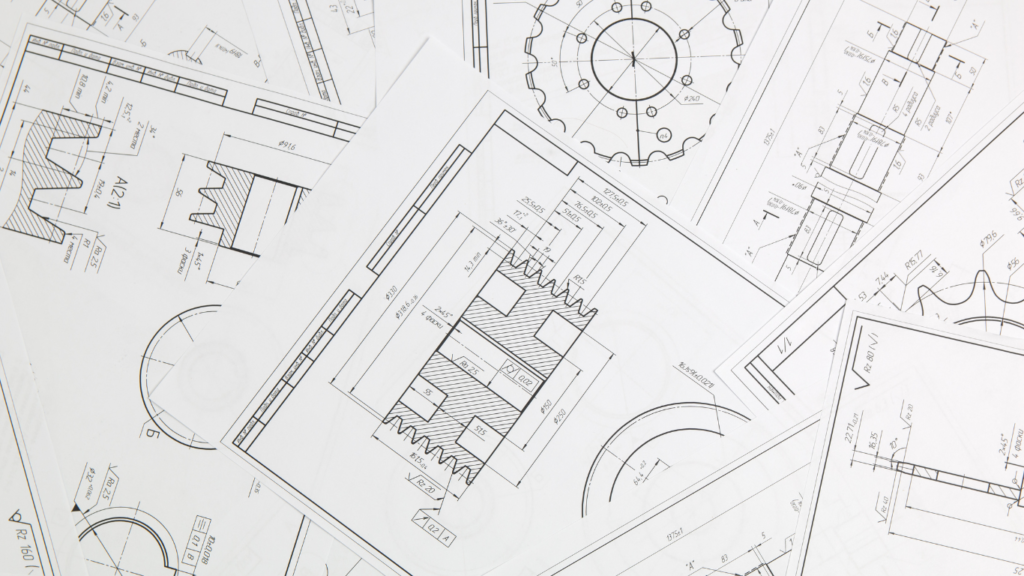転職の際には元々の職場に退職を告げる必要があります。普通の医療機関であれば、退職の意向を伝えれば特に問題なく退職できますが、なかには引止められるなどで、退職のときにすんなりやめられないケースもあります。退職についての知識と、万が一退職できない際の対処法について解説していきます。
退職できないということはあり得ない
医師とはいえ、形式上は労働者である以上、先生が希望した場合、退職できないということはありません。医療機関の就業規則で退職時は〇ヶ月前に申し出るなど書いてある場合がほとんどなので、それに従えばまず問題ありません。そもそも退職の自由は労働者の権利です。もし退職を申し出ても受理されない場合は、労働基準監督署に速やかに相談することをおすすめします。
2週間ルール
民法では、退職の2週間前に退職の告知を行えば退職できることが定められています。これは期間の定めのない場合に適用され、主に常勤の先生が対象になると思います。そのため退職を申し入れて2週間後には、特殊な場合でなければ基本的に退職出来ます。就業規則に定められている期間が例えば3ヶ月などとされている場合でも、条件を満たせば民法の2週間の方が優先されることもあります。退職をその日に伝えて、即日退職というのは流石に難しいですが、2週間の期間を待てば退職は可能です。
非常勤の先生で、たとえば一年間の契約がある場合は、契約期間中に一方的な都合で辞めることは基本的に難しいですが、たとえば急病や、家庭環境の変化など、客観的やむを得ない事情がある場合は認められるようでうす。
雇われ院長(管理医師)契約の場合は注意
注意が必要なのが、クリニックに管理医師として勤務している場合です。この場合、先生は事実上は労働者にも関わらず、法律上は労働者ではなく経営者サイドで扱われる場合があります。そのため労働者の一般的な権利を行使することができません。そのためすぐに退職することは難しいケースもあります。さらにクリニックの借り入れやリースが先生の名義になっている場合はさらに面倒です。雇われ院長の募集が注意な理由は退職する時もこのように面倒なことがあるためです。
基本的には円満退職が望ましい
当然ですが、基本的には退職する医療機関とも円満退職がベストです。たとえ前の職場に不満があっても、揉めると後味が悪いですし、医療業界は狭いのでどこで今後また縁があるか分かりません。就業規則に定められている期間よりも余裕を持って退職の意向を伝えるのが良いでしょう。一般的には引き継ぎなども含めると3ヶ月以上前には通知する方が良いです。退職する医療機関サイドとしても、時間があれば医師の求人を出したり、代診を立てるなど対策を打つ余裕があります。先生としても引き継ぎの業務を早めに済ませて、次の転職先に備えることができます。お互いにとって時間には余裕を持ったほうが良いでしょう。
まとめ
医師が退職する際は引き止めにあうことは割と多いです。本当に退職させてもらえないということは稀でしょうが、もし困った場合は今回の記事を参考にして頂ければ幸いです。