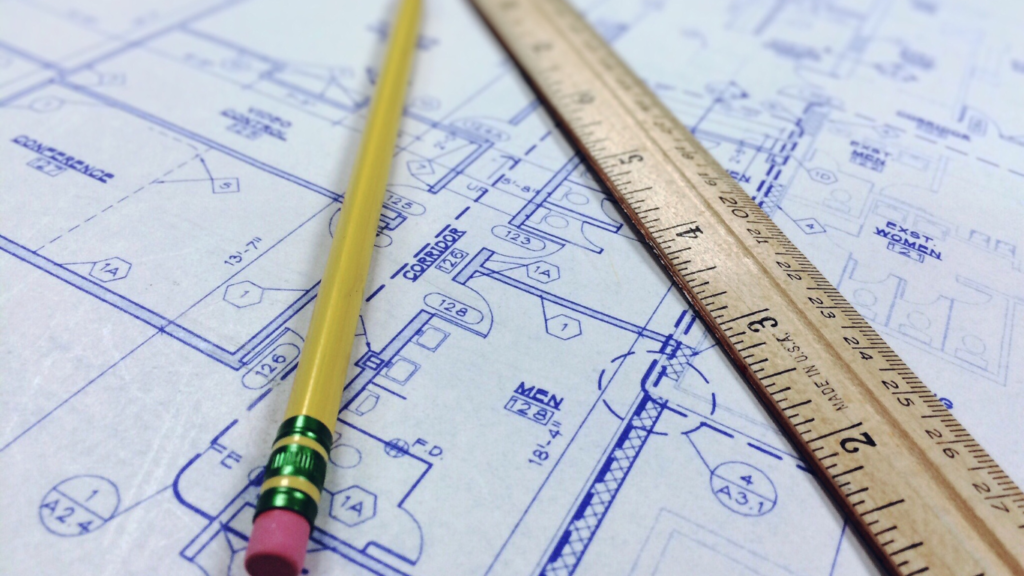若い時期には、「お金がない」こと以上に、「キャリアが思うように築けていない」「臨床能力に自信が持てない」という不安の方がずっとつらいものです。
特に臨床経験が浅いうちは、それが一番の悩みになると思います。お金は後からついてくることもありますが、臨床経験はある一定の時期に積んでおかないと、後で取り返すのがなかなか大変です。
もちろん後からキャリアをやり直すことは不可能ではありません。ただ若い先生にとっては、「臨床経験を思うように積めていない」という現実の方が、お金がないこと以上に大きな苦しみになるのではないでしょうか。
臨床能力に自信がなくてつらかった時期
私自身も、初期研修の時につまずいてしまった時期や、後期研修を始めたばかりの頃に、何が一番つらかったかといえば「まだ自分は一人前じゃない」という不安でした。
もし自分が一人で任された時、本当にやっていけるのか、解決できるのか――そう考えると、常に心の中に重くのしかかっていました。
もちろん最初は誰でもそうで、最初から一人前である必要なんてないのですが、それでも「自分は独り立ちできるのか?」という問いが、ずっと頭の中でぐるぐるしていたように思います。
時間が解決してくれることもある
ある程度の年齢になり、経験を積んでくると「時間が解決してくれることもある」と実感します。もちろん日々、一生懸命に臨床に向き合い、勉強し、上司に質問しながら必死でやってきたこと自体に意味はあります。ただ、今振り返ってみると、当時の自分は少しせき立てられていたようにも感じます。
もっと肩の力を抜いてもよかったのではないか――あまり自分を追い込みすぎなくてもよかったのではないか――今はそう思えるのです。
経験を重ねても悩みはなくならない
若い頃は「もっと経験を積めば、悩みはなくなるのでは」と思っていました。けれど実際は、臨床経験を重ねて一人で仕事をこなせるようになっても、また別の悩みは出てきます。人間である以上、常に何かしら考えることがあるのだと思います。
経験を重ねると、自分の力量や器も少しずつ見えてきます。「自分は有名なドクターのようにはなれない」「本を書いているような立派な先生にはなれない」――そうした現実を受け入れる面もあります。ですが同時に、「一般的な臨床スキルを身につけて、何とかやっていけるレベルには到達した」という実感も持てるようになりました。
つまり、悩みは形を変えて続きますが、それでも自分なりに歩んでいけるのだと思います。
臨床能力に自信が持てない時期の不安
医師免許を持っていても、臨床能力に自信がない時期というのは、不安や辛さを強く感じるものだと思います。確かに医師免許そのものは非常に有効で、初期研修を終えていれば、健診や問診などの仕事はこなせるでしょう。ただ、それだけでは現場が限られてしまうのも事実です。
特に、もし将来的に問診業務が減ったり、健診そのものが縮小・廃止されるような流れが出てきたらどうなるのか――そうした不安要素は常に残ります。免許があるから安心、というだけではなく、「臨床スキルをどの程度持っているか」という部分も、やはり自分の将来を考える上では重要になってくるのだと思います。
特に専門医資格があれば、一定のスキルが客観的に担保されます。これは転職の際にも大きな安心材料になり、「もしうまくいかなかったとしても、自分には専門医資格がある」という自信に繋がります。結果として、新しい職場を探すときにも前向きに臨めるのではないでしょうか。
ないものねだりの不安
ある程度臨床ができるようになっても、不安というのはなかなか消えないものだと思います。結局「ないものねだり」になってしまう部分があるのではないでしょうか。
スキルが上がってくるということは、同時に年齢も重ねていくということでもあります。年齢を重ねれば体力も落ちてきますし、例えば美容系など「若い先生の方が採用されやすい」現場では、不利に感じることもあるかもしれません。そういうときに「若い人が羨ましい」と思ったりすることもあります。
ただ、それはどの世代でも同じで、若い先生には若い先生なりの不安があり、ベテランの先生にはベテランならではの強みと制約があります。結局、不安というのは完全に無くなることはなく、立場が変わればまた違う「ないものねだり」が生まれるのだと思います。
キャリア初期の不安と、その先にあるもの
特にキャリアの最初、初期研修の2年、その後の後期研修3〜5年くらい、医者になってからおよそ10年弱くらいまでは「安心感が持てない」「自分は大丈夫なのか」と不安に思う時期が続くのではないでしょうか。臨床スキルに対する不安や、自分のキャリアの行き先が見えないことに悩む先生も多いと思います。
逆にその時期を超えると、ある程度年齢を重ね、家庭環境の変化なども加わって、不安の内容が少し変わってきます。臨床スキルへの不安よりも、お金や将来設計といった別の悩みが大きくなるのではないでしょうか。
結局のところ、医者に限らず「一生勉強」と言われるように、人生には常に何かしらの悩みや不安がついて回るものです。それは避けられない現実であり、むしろその時々でどう折り合いをつけるかが大切なのだと思います。
不安や悩みはずっと続く
若い頃は「これを乗り越えれば安泰だろう」「これさえクリアすれば満ち足りるだろう」と思うことが多いと思います。例えば医学部受験のとき、「入学できれば大丈夫」と考えたかもしれません。でも実際は医学部に入っても、次には卒業や国家試験が待っている。国家試験を通れば安泰かと思えば、初期研修が始まり、今度は「それを乗り越えれば」と思う。そして「専門医を取れば」、と思っても、その先にもまた課題や不安は続いていきます。
結局のところ、どの段階にいても悩みは完全には消えないものだと実感します。むしろその都度、新しい課題や不安が現れるのが現実なのだと思います。
折り合いをつけることの大切さ
もちろん、どこまでも自分に発破をかけ続けて、常に頑張り続けて定年まで突き進む先生もいるでしょう。それはそれで立派なことです。けれども、やっぱりそれでは疲れてしまう先生も少なくないと思います。私自身もその一人です。
だからこそ、どこかの時点で「無理を続けるのではなく、ここで折り合いをつけよう」と考えることが必要なのだと、最近になって強く感じるようになりました。頑張り続けるだけではなく、自分の心身や人生全体を見ながら、納得できるバランスを見つけることも大事なのだと思います。
若い先生へ、そして同世代の先生へ
この文章をわざわざ読んでくださっている先生は、きっと若い先生や、私と同じくらいの世代の先生が多いのではないかと思います。やはり医師として働いていれば、臨床のことやキャリアのこと、あるいは人生そのものについても、いろいろと迷いが生じてくるものですよね。
私自身の経験から言えば、どこかの段階で「折り合いをつけながら」「あまり自分を追い詰めすぎずに」やっていくことが、長く臨床を続けるコツなんじゃないかと最近は感じています。
もし先輩の先生方がご覧になっているなら、本当は「どうやって折り合いをつけてきたのか」をぜひ伺ってみたいところです。