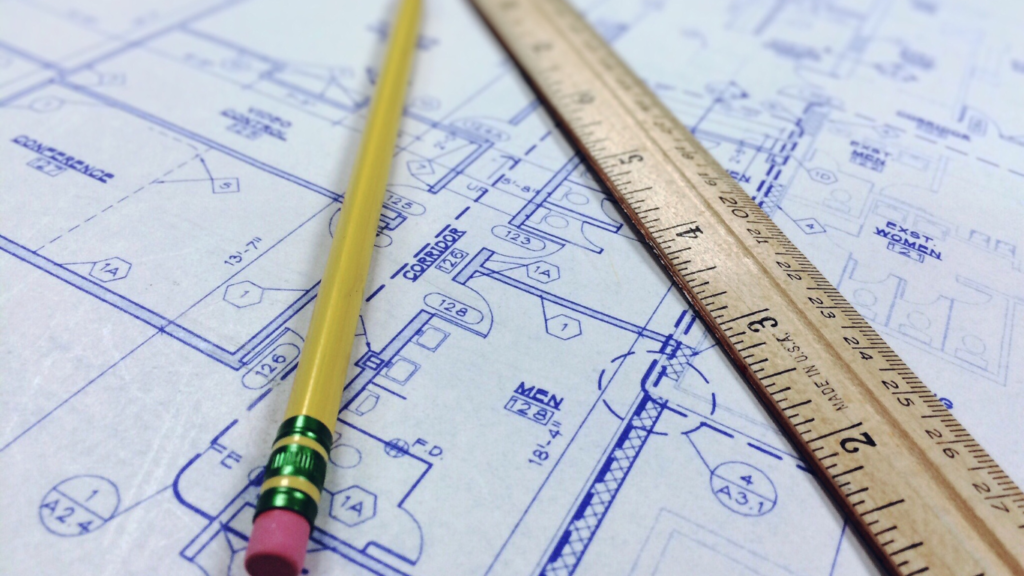医者として働く中で言えることですが──辛い時は、いつでも逃げても大丈夫です。
医者というのは、子どもの頃からずっと努力を積み重ねてきた方が多く、その分プライドも高いものです。だからこそ「辛くても頑張らなければ」と自分を追い込みすぎてしまう先生も少なくありません。もちろん、その結果として乗り越えられる場合もあるでしょう。
しかし一方で、限界まで頑張り続けた結果、折れてしまう先生も実際に多いのです。本当に「これは無理だ」「続けられない」と感じたときは、無理に耐える必要はありません。客観的に見て「頑張れば何とかなる」場面もあるでしょうが、先生ご自身が「どう考えても無理だ」と判断したなら迷わず逃げて欲しいと思います。
今まで失敗をしてこなかった先生へ
今まで大きな失敗をせず、道を大きく外れることなくやってこられた先生ほど、「途中でそれる」ことに強い抵抗を感じるかもしれません。
しかし、現実にはどう頑張っても乗り越えられない状況、そこで踏ん張るのが現実的ではない状況というものが存在します。
そういうときは、自分を責めたり「弱いからだ」と思う必要はありません。その時点で無理をして続けることの方が、むしろ大きなリスクです。
だからこそ、その場は「逃げる」選択をしてほしいのです。逃げることは恥でもなんでもなく、ご自身を守るために必要な行動です。
どんな状況でも「無理だ」と思ったら離れていい
それは初期研修でも後期研修でも、あるいは専門医を取得した後に一人医長として赴任した場合や、大学院で論文執筆に追われている場合など──医師のキャリアにはさまざまな場面があります。
しかし、どんな状況であっても「これはもう無理だ」「続けるのは危険だ」と感じたなら、その場を離れる決断をしてほしいのです。
若手の先生に限らず、中堅以上の先生でも心が折れそうになることはあります。むしろ中堅の先生ほど、これまで頑張り続けてきたからこそ「今さら休めない」と思い込んでしまう傾向が強いのかもしれません。
さらに、住宅ローンや車のローンなど経済的な事情を抱えている方もいるでしょう。「辞めたら生活が成り立たない」と不安になるのも当然です。
それでも、まずいと思ったときは無理をせず、その場を離れてください。心身を壊してしまえば、ローンどころか人生そのものが立ち行かなくなるからです。
最悪のパターンは「働けなくなること」
医師として避けたい最悪のパターンは、心が折れてしまい、その結果「働けなくなる」ことです。
精神疾患などで以前のように復帰するのが難しくなり、仮に労働負荷が軽減された職場であっても続けられなくなる──そうなってしまうと、せっかくの医師免許も、積み重ねた経験や博士号といった経歴も、活かせなくなってしまいます。
これは非常にもったいないことであり、ご本人にとっても、そしてご家族にとっても大きな喪失です。社会的にも、経済的にも、そしてなによりご自身の気持ちとして一番辛い結末ではないでしょうか。
もちろん一番避けたいのは、自ら命を絶ってしまうようなケースです。しかし、そこまで至らなくても「働けなくなること」自体が、医師にとって非常に大きなのリスクの一つなのだと思います
無理な現場は「方向転換」すればいい
たとえ様々な事情があったとしても、「これは無理だ」と思う現場なら、思い切って離れてしまえばいいのです。2〜3か月休むのもよし、場合によっては半年や1年休んで心身を回復させるのもよし。その上で別の現場を探して再スタートするのは、決して失敗ではなく**方向転換(ピボット)**です。
むしろ、その後により良い職場と出会えたり、QOLが高まったり、自分の生活を大切にできるようになったとすれば、それは失敗や挫折ではなく、成功だと言えるのではないでしょうか。
確かに休む決断は辛いものですし、最初は不安も大きいと思います。しかし、無理をして続けた結果、健康も仕事もすべて失ってしまうよりは、ずっと良い未来につながります。方向転換を恐れずに、自分のペースで生きていくことは十分可能です。
辛い時は正直に伝えることも大事
ある程度臨床経験のある先生なら、基本的に将来困ることはほとんどありません。迷いやすいのは、研修中だったり、専門医や博士課程の途中にいる先生かもしれません。たしかにこれらを中断するには抵抗があると思います。しかしそれでも「本当にもう無理だ」と思ったら一人で抱え込まずに離れて欲しいと思います。
もちろん「すぐ退職した方がいい」という意味ではありません。まずは信頼できる上司に「今のままでは続けられない」と正直に相談してみてください。それだけで労働負荷を減らしてもらえたり、論文の期限を延ばしてもらえたりと、思った以上に状況が変わることは多いのです。
多くの先生が「他の人に迷惑をかけてしまう」「自分だけ楽をしてはいけない」と我慢してしまいがちです。でもそんなこと気にしなくていいんです。何より大事なのは、周囲の目よりも先生ご自身の体調です。限界を超える前に、「もう無理です」と声をあげてください。
急に辞めても、恨まれることはない
先生も見たことがあると思いますが、医療業界では「急に辞めてしまう」「急にメンタルを崩してしまう」ケースというのは決して珍しくありません。外来を突然やめたり、ある日から職場に来なくなる先生もいます。
もちろん現場は一時的に大変になりますが、それでも「どうしようもない」「裏切られた」なんて思う人はほとんどいません。むしろ、見ている人にはちゃんとわかるんです。「あの先生、最近すごく辛そうだな」「このままでは折れてしまうかもしれないな」と。
だからこそ、急に休んだり、辞めたりしても恨まれることは思っているよりありません。むしろ「よくここまで頑張ったな」「あの状況では仕方がないな」と思うのが普通です。全員が全員そうではないかもしれませんが、普通に心を持った人間ならきっとそう感じるはずです。
だから気にしなくていいんです。辛ければ休んでいい、離れていい。それで人生が終わるわけではありません。
周りはすでに気づいている
実際のところ、先生ご自身が「もう無理かもしれない」と感じている時点で、周りのスタッフや同僚もすでに気づいていることが多いんです。同僚の医師に限らず、看護師さんや事務スタッフも「あの先生、かなりきつそうだな」と感じているものです。
だから、思い切って「少しきつい」と伝えてみるだけで、意外とスムーズに業務の軽減や配置換えといった対応をしてもらえることがあります。場合によっては「しばらく診断書をもらって休んではどうか」と提案されるケースもあります。
常勤医であれば、社会的なセーフティーネットも用意されています。
- いきなり解雇されることはない
- 傷病手当金が支給される(額は多くないが生活の支えになる)
- 社会保険料も継続可能(在職中であれば手続き不要)
- 職歴上も不利になることは基本的にない
つまり「休む=キャリアの終わり」ではなく、制度を活用して体調を立て直すことができます。必要以上に不安に思う必要はないんです。
声をかけられたら、もう危険信号
中には「先生、最近辛くないですか?」「体調大丈夫ですか?」「顔色悪いですよ」と周囲から声をかけられる先生もいると思います。これは非常に重要なサインです。
医師に対して体調のことを直接聞くのは、よほどのことがない限りありません。つまり、そう声をかけられた時点で 「相当まずい状況だ」と周囲も認識している ということです。
ご自身が思っている以上に、客観的には危険な状態にある可能性が高いのです。倒れる寸前だと考えて間違いありません。
ですから、その段階に来ている先生は、もう迷わず休んでください。体調を守ることは、自分自身にとっても、患者さんにとっても、そして一緒に働く周囲の人たちにとっても一番大切なことです。
休むときは「何も考えない」でいい
「休んでどうするか」を考えてしまう先生は多いと思います。ですが、体調が限界に近い時は、復帰の期限やその後のキャリアのことなど考えなくても大丈夫です。
「1ヶ月で直そう」「2ヶ月で復帰しよう」と期限を決める必要もありません。むしろ、そういうことを考えずに、まずは徹底的に休むことが一番大切です。
休養によって体調が回復し、気力や思考力が戻ってくれば、自然と「次にどうすればよいか」が見えてきます。そのときに、元の職場に配慮をお願いして戻るのも十分現実的な選択肢です。
もちろん、同じ労働負荷やハードワークで戻ると再発する可能性があります。ですから、復帰する際には 業務の軽減や勤務形態の調整 をお願いすることが大切です。日当直や当直の免除、また時短勤務など配慮してもらえることは少なくありません。
元の職場に戻れないときは転職も選択肢
場合によっては、元の職場に戻るのが難しいこともあります。特に、労働負荷の調整が難しい場合や、人間関係でトラブルがあった場合は、転職の方が現実的です。
無理に交渉して元の職場にとどまるよりも、新しい環境へ移った方がスムーズに再スタートできることもあります。実際に、「ハードワークがきつすぎて続けられない」「メンタル的に限界だから労働負荷を軽くしたい」と伝えても、採用してくれる職場は十分にあります。
私自身も「もう辛すぎて今の職場は続けられないので、新しい職場を探しています」と率直に伝えました。それで問題なく受け入れてもらえましたし、むしろそう話して理解してくれる職場の方が、お互いにとって良い関係を築けると思います。
転職理由は必ずしもきれいに取り繕う必要はありません。先生自身が安心して働ける場所を探すことこそ、長く臨床を続けるための大切な一歩だと思います。
細くても長く続けることの大切さ
休んだ経験のある先生も、「あのとき休んで良かった」と振り返ることが多いと思います。数ヶ月、あるいは1年休んだとしても、10年・20年という長いスパンで見れば、その方が結果的に良かったと感じられるはずです。
逆に、無理をして働けなくなるまで頑張ってしまい、キャリアや生活が完全に途切れてしまうことの方が大きな損失です。大事なのは「0か1か」で考えないことだと思います。少し形を変えてでも、仕事を細く長く続けていく方が、先生にとっても社会にとっても価値のあることだと思います。
働き方にも選択肢はあります。
- 週5日の常勤だけが全てではない
→ 週4日、場合によっては週3日でも常勤扱いになる病院もあり、日数を減らすのは現実的で有効な方法です。 - 非常勤という選択肢
→ 週1〜2日の外来でも臨床を続けることはできますし、ブランクを避ける意味でも有効です。 - 収入面も工夫できる
→ 労働負荷を減らしても、選び方によっては収入が大きく下がらない、むしろ増えるケースもあります。非常勤を上手に利用すれば、常勤よりも勤務日数を抑えて、収入を維持することも現実的です。
大切なのは「週5常勤にこだわること」ではなく、「自分が無理なく臨床を続けられる形を見つけること」です。細くても続けることで、キャリアは守られ、結果的に大きな力になるはずです。
非常勤という働き方もあり
非常勤で数年やってみて、「やっぱり常勤に戻りたい」と思えば戻ればいいだけです。逆に、非常勤という働き方が自分に合っていると感じれば、そのまま続けても問題ありません。
非常勤にはデメリットもありますが、実は常勤にはないメリットも多くあります。労働負荷を調整しながら収入を得られるだけでなく、勤務日数や場所を柔軟に選べるのも大きな魅力です。実際、非常勤を選んで「こちらの方が自分に合っている」と感じる先生も少なくありません。
非常勤は単なる「妥協」ではなく、完成された労働形態のひとつだと私は思います。
つまり、「以前の働き方に戻らなければならない」というこだわり自体を手放してもよいのです。
医師免許と健康があれば大丈夫
繰り返しになりますが、医師であれば「医師免許」と「心身の健康」さえあれば、何とかなります。
たとえ今が苦しい状況でも、この2つがあれば最悪の事態に陥ることはありません。
確かに、10年前のように恵まれた環境ではなくなりつつあり、インフレや制度の変化によって医師に不利な点が出てきているのも事実です。
しかしそれでも医師が「食っていけない」状況にはなりません。平均的な生活よりも、むしろ良い水準の暮らしを維持できるのが現実、これはまだ当面の間続くでしょう。
だからこそ、今の職場を離れたり、転職でつまずいたり、一度挫折してしまったとしても、絶望する必要はまったくありません。
むしろ少し距離を置いて冷静に振り返ってみると、「意外に平気だ」と気づけるはずで
命を最優先に
今回一番お伝えしたいのは、体調を崩しきってまうこと、命を落とすことだけは避けてほしいということです。
残念ながら、それは実際に起こり得ることです。だからこそ、そこだけは絶対に守っていただきたいと思います。
経歴やキャリア、名誉やお金──それらはもちろん大事ですが、命を失ってしまえば何も残りません。
どんなに立派な経歴や資格を持っていても、生きていなければ意味がないのです。
だからどうか、何よりもまず「命を優先する」ことを忘れないでください。
そこを守りさえすれば、人生も仕事も必ずやり直せますし、どんな状況でもまた道は開けていくはずです。
ご家族へのお願い ― 医者を止められるのは身近な人です
もし医師のご家族がこのサイトを偶然見てくださっているなら、どうか覚えておいて欲しいことがあります。
「おかしいな」「普段と違うな」と思ったら、ためらわず先生を止めてあげてほしいのです。
ご両親、配偶者、あるいはお子さん──誰であっても、身近な人が気づくサインはあります。
・最近元気がない
・眠れていない
・食欲が落ちている
・痩せてきた
・顔色が悪い
・電話の声が沈んでいる
こうした変化は、ご家族だからこそ気づけるものです。
医者は普段は冷静で高い判断力を持っていても、自分のことになると途端に判断ができなくなる生き物だと私は思っています。患者さんの命を守ることはできても、自分の命や健康については鈍くなってしまうのです。
だからこそ、最終的に止められるのは周りの人だけです。
私自身も、自分では止められず、最後にブレーキをかけてくれたのは周りの人でした。今振り返ると、あの時止めてもらえなければ、自分はもうここにいなかったかもしれません。本当に感謝しています。
もし「これはまずい」と思ったら、どうか休ませて、先生本人の代わりに職場に電話をしてください。「しばらく休ませます」と伝えてあげればいいのです。現場も多くの場合わかってくれます。頑張りすぎていることを知っているからです。
それがご本人を守るだけでなく、ご家族全体を守ることにもつながります。
どうかためらわずに、救い出してあげてください。