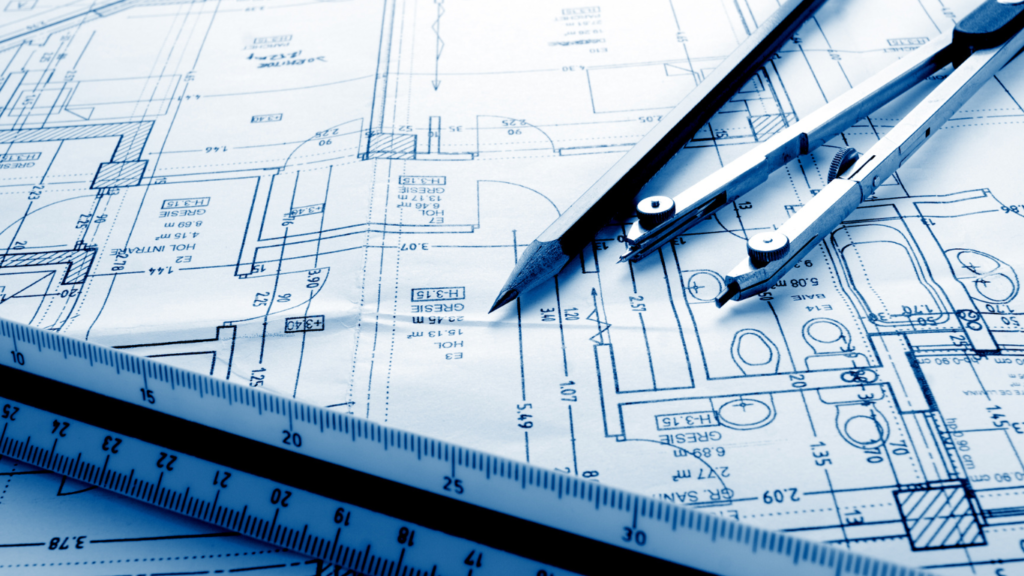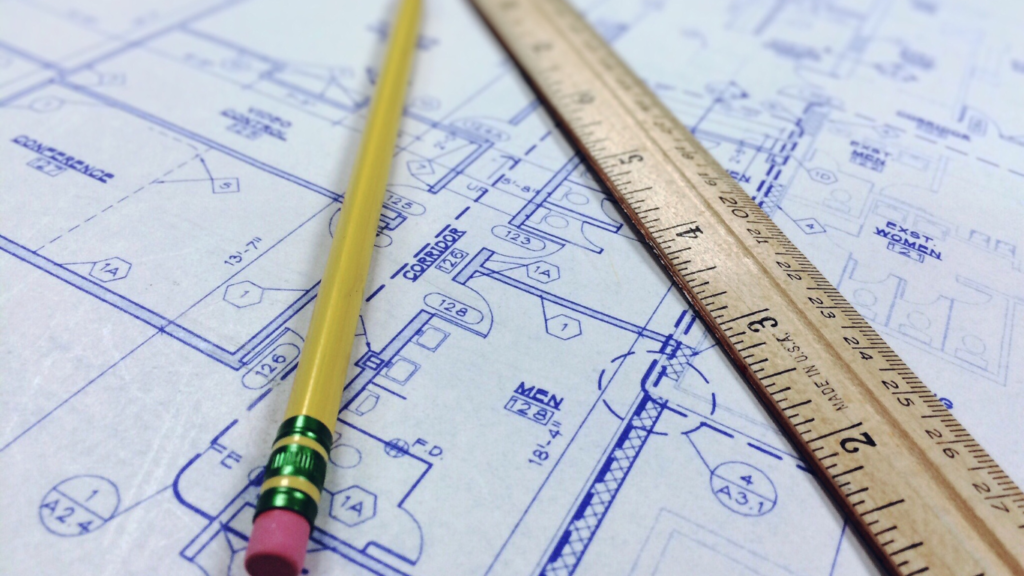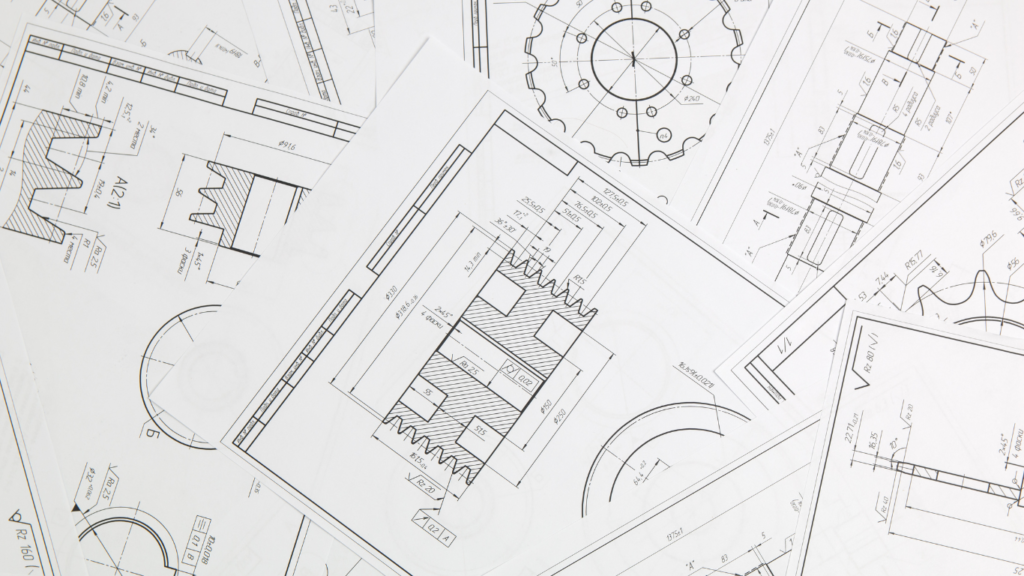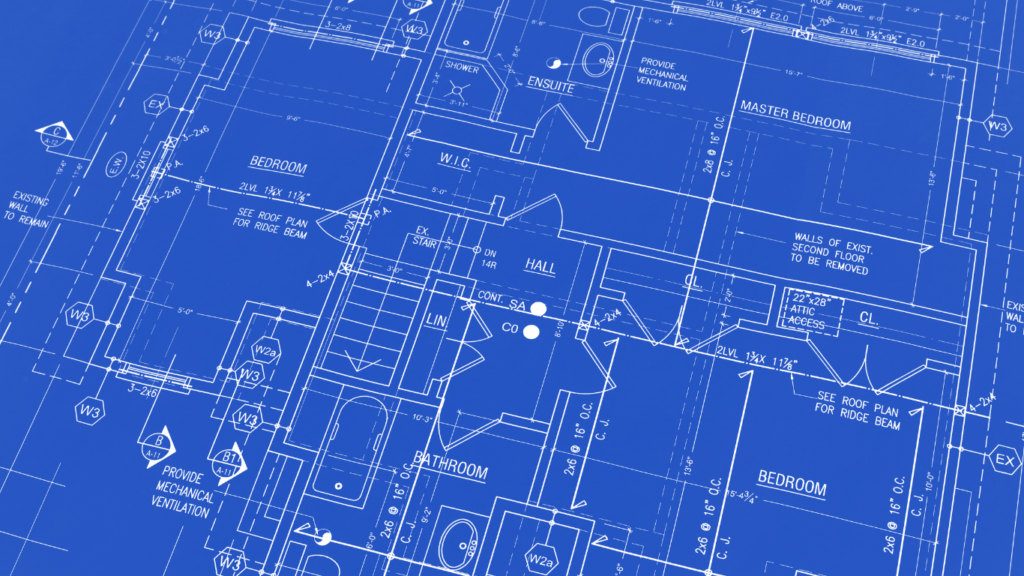
転職を考える際、「どの程度のスキルが求められるのか」を気にする先生は多いと思います。
しかし実際には、採用側は臨床能力を先生が想像するほど重視していないケースも多いのです。
もちろん外科の特殊手技や一部の専門分野ではスキルが問われますが、一般的な診療業務では「これができないと採用されない」というほど特殊な能力が求められることはあまりありません。
加えて、臨床能力は実際に働き始めてからでないと判断できない部分が大きいのも事実です。専門医資格などがあれば一定の保証にはなりますが、それでも個人差がありますし、証明が難しい要素でもあります。採用側から見れば、最終的には「入ってから判断するしかない」というのが現実です。
むしろ重視されるのは、
・コミュニケーション能力
・社会人としての基本的な振る舞い
といった人間性の部分です。
そのため、臨床能力は医師自身が思うほどには転職において重要視されない傾向があると感じています。
これができないと不利になる?
よくある心配として、「自分は手技があまり得意ではないから、転職で不利になるのでは」と感じる先生がいます。例えば内科医でCVの挿入が苦手なケースなどです。
しかし実際には、それだけを理由に転職が不利になったり、採用を断られるケースは非常に少ないと思います。極端な話、入職後に「この手技は得意ではない」と伝えたとしても、それでクビになることはまずありません。
不得意なことがあるからといって転職を躊躇するのは、むしろもったいないことです。
苦手な部分は他の先生に補ってもらい、自分は得意分野で力を発揮すれば十分に貢献できます。
もし不安であれば、面接や入職前の段階で率直に伝えておくのも一つの方法です。あらかじめ理解を得ておけば、後々のストレスも少なく、むしろお互いにとってプラスになる可能性が高いでしょう。
コミュニケーション能力の問題
実際のところ、臨床能力そのものが問題になるケースは多くありません。
普通に臨床経験を積んできた先生であれば、標準治療から大きく逸脱するようなことはまずなく、臨床スキルが理由で困る場面は少ないと思います。
むしろ現場で問題になりやすいのは、コミュニケーションの部分です。
例えば、感情的に怒ってしまう、当たりが強い、他のスタッフと衝突してしまう──こうした人間関係のトラブルが原因で職場に居づらくなるケースの方が圧倒的に多いと感じます。
つまり、採用されないとすれば「臨床能力不足」よりも「コミュニケーション上の問題」が理由になることの方が多いのです。
採用側の心理
採用において、臨床能力はもちろん大事ですが、事前に正確に評価することはできないというのが現実です。専門医資格は一つの目安にはなりますが、資格がなくても優秀な先生はいますし、逆に専門医を取ったばかりで経験が浅い先生もいます。採用側もそれを理解しており、面接で臨床能力を完全に見極めることは不可能だとわかっています。
そのため、病院側がより重視するのは人間性や社会人としての振る舞いです。
例えば、
・面接に遅刻しない
・きちんとした服装で来る
・必要書類を忘れず持参する
・丁寧な受け答えができる
といった、ごく当たり前のことができるかどうか。
意外かもしれませんが、こうした基本ができない先生も一定数おり、採用側にとってはそれが大きなマイナス評価になります。
逆に言えば、社会人として普通の振る舞いができれば、それだけで大きな問題になることはまずありません。その上で条件のすり合わせをして合意できれば採用は十分可能ですし、むしろきちんとした対応ができる先生は引く手あまたで、条件も選びやすい立場になれるでしょう。
まとめ
転職を考えるとき、多くの先生は「自分の臨床能力は十分だろうか」と心配されます。
しかし実際には、採用側は臨床能力を想像ほど重視していません。特殊なスキルが必要な場面は一部に限られ、多くの場合は「入ってから判断するしかない」というのが現実です。
むしろ重視されるのは、
・コミュニケーション能力
・社会人としての基本的な振る舞い
といった、人間性の部分です。
不得意な手技があっても、それだけで不利になることはほとんどありません。率直に伝えておけばお互いに納得して働けますし、他の先生に補ってもらう形で十分貢献できます。
採用側も、専門医資格や経歴以上に「人として安心して一緒に働けるか」を見ています。遅刻をしない、丁寧に受け答えする、必要書類をきちんと揃える――そんな基本的なことができる先生は、むしろ引く手あまたです。
つまり転職においては、臨床能力そのものよりも人間性と誠実な対応が重要です。
その点を意識して臨めば、先生が思う以上に転職のハードルは高くないはずです。