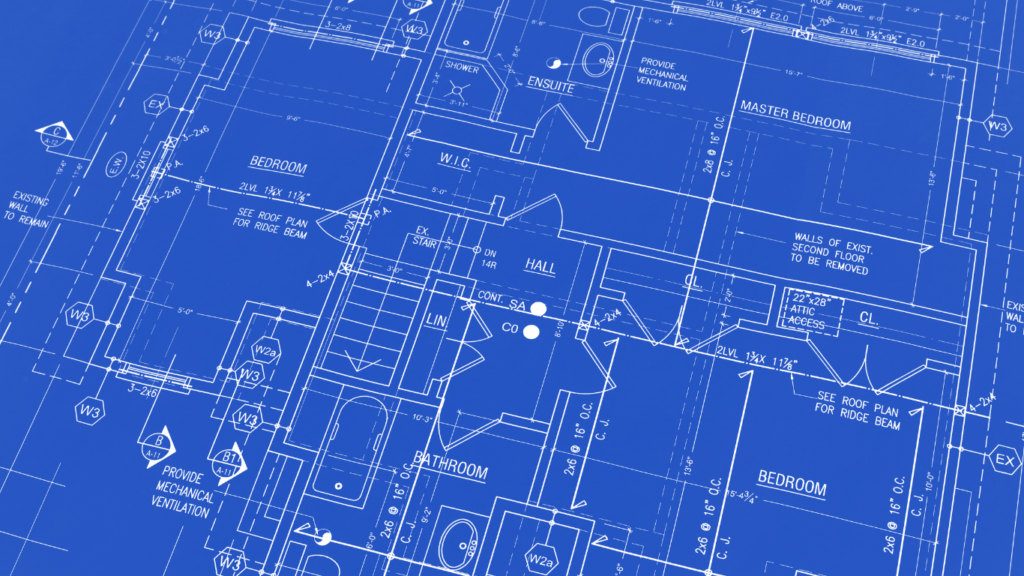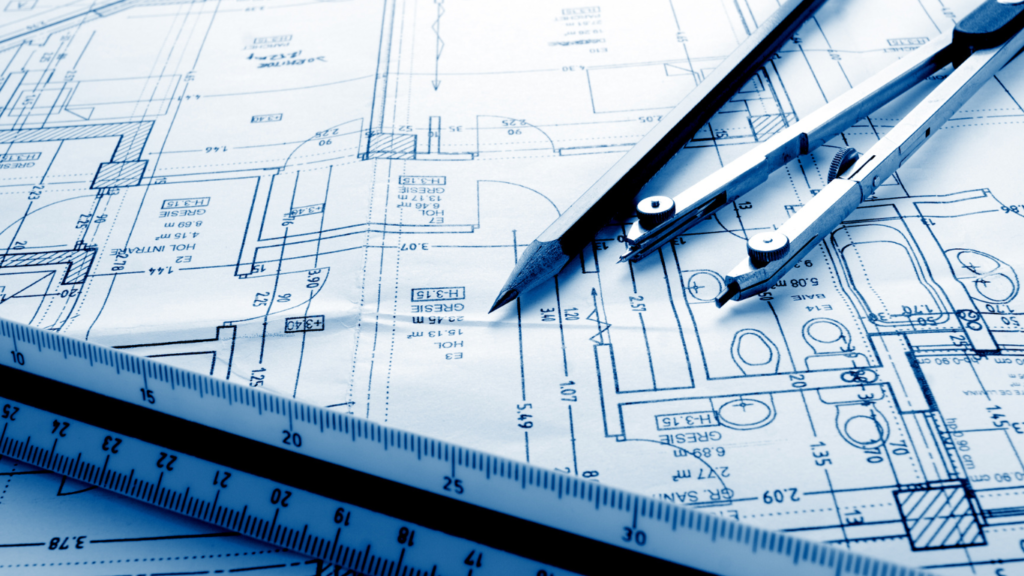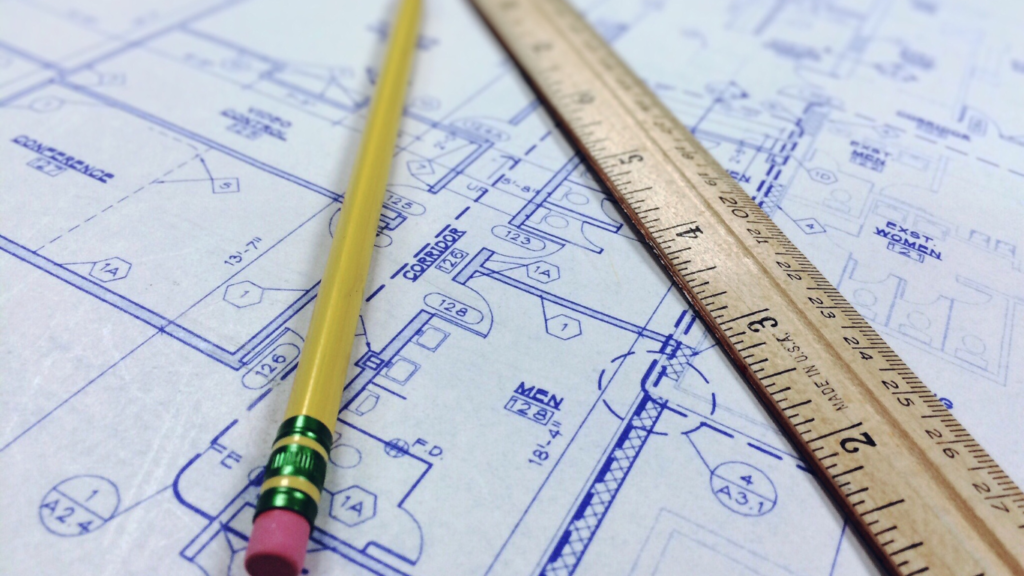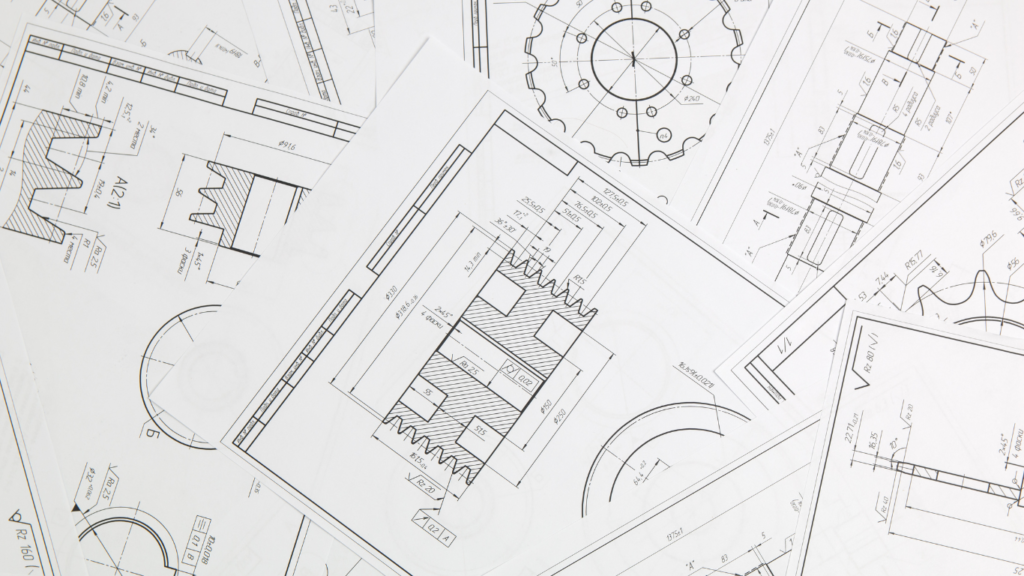このサイトをご覧の先生のなかには、現在非常勤で勤務されている先生や、非常勤でお仕事を探されている先生もいらっしゃると思います。非常勤のデメリットの一つは、常勤よりも雇用形態が不安定で、雇い止めにあうリスクが一定の確率で存在することです。その分給与が高めであるというメリットもありますが、いつ仕事を失うかわからないという不安は嫌なものです。
しかしながら、非常勤にも雇用を守る法律が存在します。通常、非常勤の先生は、期限を設けて契約することが普通です。勤務先により、半年だったり1年だったりとまちまちですが、5年以上勤務する見込みの場合、次の契約の際に、有期契約から無期契約に雇用形態を転換することが可能です。今回は非常勤勤務のいわゆる無期転換ルールについてご紹介します。
無期転換ルールとは?
ルールの詳細については、厚生労働省の資料に分かりやすくまとまっていますので、こちらもご参考いただき、一部ピックアップしてみてみます。無期転換ルールについて
無期転換ルールは、医療機関と先生の間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、先生からの申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されるルールのことです。
ポイントは、①5年以上の契約があること、②先生から申し込みを頂く必要があること、③そして先生が申し込んだ場合、医療機関側は先生の申し出を断ることはできません。
申し込みができる期間については、厚生労働省の資料から引用して下記に示します。
要約すると、契約更新を繰り返して、5年以上勤務する見込みが存在した段階で、有期契約から無期契約への契約変更を申し込む権利が発生します。
正確には、一定期間仕事を休んでいる期間があったりすると、カウントがリセットされることもありますが、多くの先生には関係ないと思います。
無期転換ルールの例外
高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者には、無期転換ルールの例外があります。もちろん医師も該当しますが、これは雇用主からするとかなり要件が厳しく、通常の診療に従事している場合は適用されないことが多いと思われます。
無期契約になっても待遇は変わらない
無期転換ルールを行使することで、業務内容が極端に変わったり、給与が下がったりすることは許されません。無期契約になることを好まない雇用主は少なくないと思われますが、これを阻害するような行為は法で規制されています。そもそも無期転換ルールは労働者を守る法律であるためです。
実際のところは
実は私も無期転換ルールは最近知ったもので、これを行使して、無期契約に変更した先生を直接は存じないので、なんとも言えません。しかしこのルールの勉強をしていて、ふと思い出したことがあります。
以前勤めていた病院で、ちょうど5年で契約終了となって退職された知り合いの先生がいらっしゃいました。その先生は非常勤で週に数回、外来を担当されている先生でした。その先生としては、契約は当然更新されるものと思っていたらしいのですが、突然上記のタイミングで次回契約は更新しない旨を伝えられたそうです。
今振り返ると、無期転換ルールを行使され、辞めさせることができなくなることを恐れた病院が、権利が発生する前に雇い止めを行ったのかもしれません。(本来そのようなことはあってはならないのかもしれませんが、、)その先生は患者さんからの評判は良い先生でしたが、一部事務さんに当たりが強い面があったように思われ、、、そこが影響した可能性があるかと推測しています。事務さんを含め一緒に勤務するスタッフさんには、日頃から丁寧に対応することが大切なのかもしれません。
私ならどうするか?
実際に私が無期転換ルールの権利が発生した場合に行使するかどうかという話ですが、なんとも言えません。雇用主の立場を思うと、無期契約の非常勤医師の負担やプレッシャーは少なくないものと考えられます。万が一、経営が苦しくなったときに、真っ先にカットするのは給与が高い非常勤医師であるからです。
他の非常勤医師が多くいる中で、このルールを行使すれば、たしかに生き残れる可能性は高くなります。しかしその職場の居心地がどうかというと、少々疑問ではあります。また本当に経営が破綻するようなことがあれば、結局は職を失ってしまうことになります。
結局のところ私としては、どうするのか今でも結論は出ておりません。しかしもし現在勤めている職場で働けなくなった場合に備えて、常に転職市場のチェックはしております。私としては、一つの職場に執着をするよりも、何かあった際にフットワーク軽く動ける方が、結果的に自分が生き残れる可能性が高いのではないかと考えています。
転職市場をチェックすると言っても特殊なことはしていません。求人会社のメールマガジンを3社ほど購読し、一日数分ほど目を通すくらいです。気になったものがあれば保存してストックしておきます。いい求人が流れてきたら少し詳しく見て、動向を掴むように努めています。